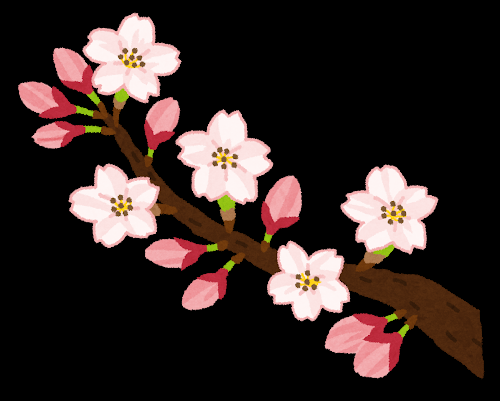健康保険任意継続について
会社を引退し、今までは考えたこともなかった(方も多いと思われる)健康保険。
退職後の健康保険は、どうなるのか心配されている方も多いかもしれません。
そこで、健康保険についてお話したいと思います。
まず退職後の健康保険についてですが、
概ねの方は以下3つより選ぶことになります。
①国民健康保険に入る。
②任意継続をする。
③ご家族の健康保険に被扶養者として入る。
上記3つのうちどの健康保険に加入した方が良いかは、一概には判断できず、
個々人の状況(前職の収入や扶養している人数など)によって異なってきます。
ここでは、上記3つの「退職時に選ぶ健康保険」の内「②の任意継続」についてご説明したいと思います。
◇まずは基礎知識
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加入要件
1、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
2、資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
被保険者期間:任意継続被保険者となった日から2年間
保険料:退職時の標準報酬月額×10.12%(福岡県、平成26年度9月以降の場合)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
任意継続の保険料と聞くと、
「今まで納めていた保険料の倍負担なので支払額が大幅に増えそう」と思われるかもしれませんが・・・必ずしもそうとは言えません。
◇標準報酬月額には上限がある!
前提として、保険料は「退職時の標準報酬月額」×「都道府県ごとに決められた料率」で計算しますが、「任意継続の時だけ」金額が大きい場合は保険料が打ち止めされます。
具体的には標準報酬月額の上限が28万円で標準報酬月額が50万円であろうと100万円であろうと保険料は、月額28,336円(介護保険料除く)となり、退職時の給与が大きい方は任意継続がお得な場合もあります。
他にも、扶養の人数や居住地など様々なケースでお得か変わってきます。
どちらが得となるかご不明の場合は、川庄公認会計士事務所担当者までご相談下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 麻生
節税対策 2024-04-24
仮装通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時、償 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。 ...