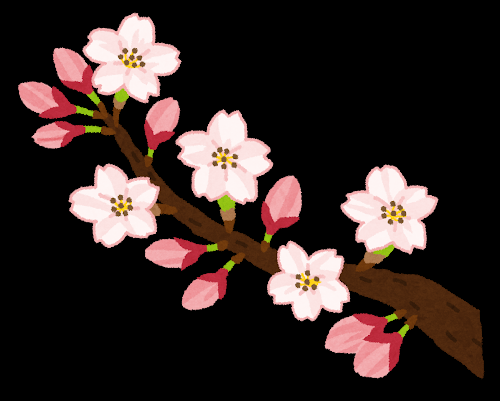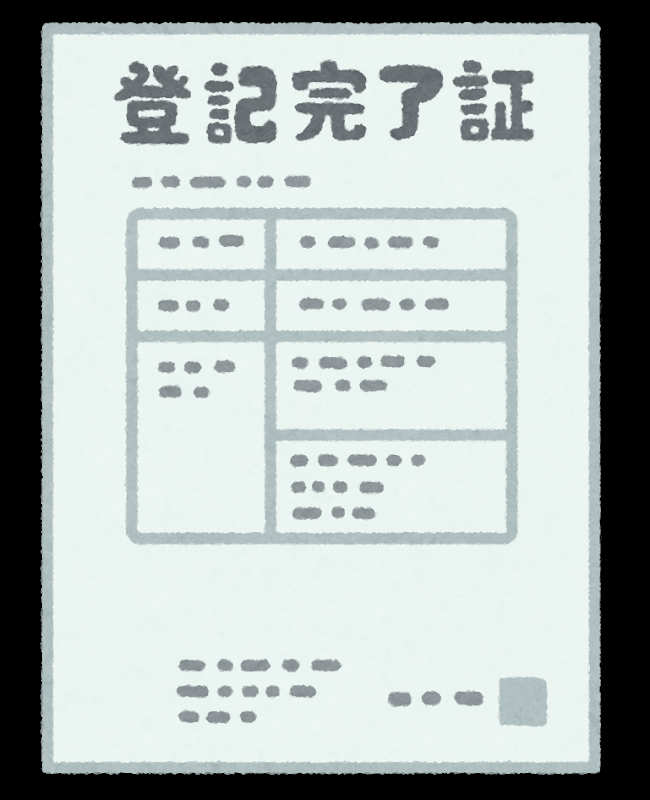人生100年に向けて
| Posted by |  |
川庄 康夫 Yasuo Kawasho |
長寿社会の到来
私が大学を卒業する頃の企業の定年は55歳でした。人は定年後にそう遠くなく死亡していましたので、当時年金の問題が取り上げられることもありませんでした。
厚生労働省がまとめた2018年の簡易生命表によると、2016年の国民の平均寿命は男性が80.98歳、女性で87.14歳です。また、90歳まで生存する割合は男性24.2%、女性48.3%で「人生90年」の時代が現実味を帯びてきました。
我国で90歳以上の方は200万人以上います。人生100歳も夢でなくなってきましたが寿命が長くなれば、その経済的な裏付けが必要となります。
① 公的年金の受け取りを先延ばしにする
英国等ヨーロッパの国々では年金の受け取りは67歳~68歳で、それに比べると我国の65歳での受け取りは早い方です。
年金の受け取り開始時期を65歳から70歳に繰り下げれば1.42倍の年金を受け取ることができます。
現在月額21万円受け取れる人が5年間受け取りを延長すれば月額29.8万円となり、約8.8万円多く受け取ることができます。
今は人手不足の時代で働く気があれば、働くことができます。定年後更に5年間働くことで生涯に受け取る終身年金の恩恵を享受できます。
② 確定拠出年金の活用
確定給付企業年金は運用の利回り低下やマイナス金利の影響で運用が難しくなっていますので、企業はこの年金制度から確定拠出年金へ移行しています。
この年金制度は60歳まで毎月1定額を積み立て(拠出)し、加入者自身が運用、預入する商品を決めて老後資金を作る年金制度です。将来受け取る年金額は、運用成果によって変動します。
DC制度(又401K)と呼ばれ、少子高齢化で公的年金の減額が避けられないので公的年金に上乗せする新たな年金制度として導入されました。
この年金制度は企業型と個人型があり、個人型はその加入が伸び悩んでいましたが、2017年1月から自営業者やDC制度を導入していない会社の社員に限られていた加入者の範囲を拡大し、公務員、主婦、企業型を導入している企業の会社員まで加入できるようになりました。
個人型確定拠出年金のメリット
■積み立て時の掛金は全額所得控除となります。例えば毎月1万円で年12万円積み立てると20%の税率の人は2,4万円税金が安くなります。掛金の上限は81.6万円です。
金融商品の運用益には税金(20.31%)がかかりますが、個人型の運用益は非課税です。
■積み立てが終了して受け取る時は雑所得として課税されますが公的年金控除が受けられます。
今、個人型で積み立ててある人の大部分は元本確保型の積み立てで運用しており、税控除のメリットは主に受けていますが政府はリスクを取った運用へ変換する方向へと誘導しようとしています。我国の成長戦略の一環として個人資産を投資資金へ持ち込むことを目指しています。
③ 老後の生活資金の確保を目指して
現役時代に税制優遇のもとで積み立て、資金が必要になったら引き出し、又税の優遇を受けることが必要です。
総務省の全国消費実態調査によると、高齢無職2人以上の月間収入金額は年金等で23.9万円支出は27.3万円のため、毎月の不足金額は3.4万円となり年間40.8万円(3.4万円×12ヶ月)を年金以外で賄う必要があります。
2人以上の高齢者無職世帯(世帯主が60歳以上)は平均2400万円程の貯蓄を保有しています。高齢者世帯は十分な貯蓄を持っているように見えますが、高齢者世帯の約38%が保有する貯蓄は1000万円未満であります。そのうち100万円未満の世帯は7%以上存在します。
人口減少と高齢化が加速し、国家財政は限界に近いため、いざとなったら生活保護へ逃げ込んでも現在のように最低限の生活がおくれる保障はないかもしれません。そのため老後までの長い時間軸に沿った資産形成をすることが必要です。
川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

|
Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫
|
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。 ...
相続・事業承継コラム 2024-03-22
4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...