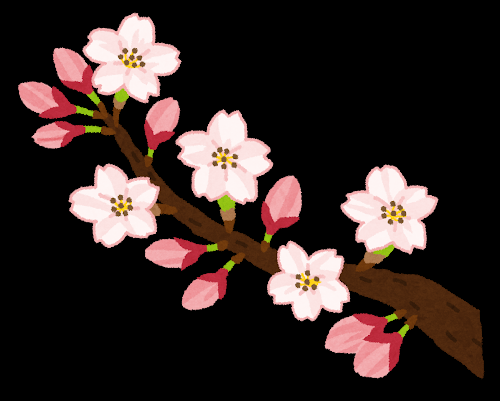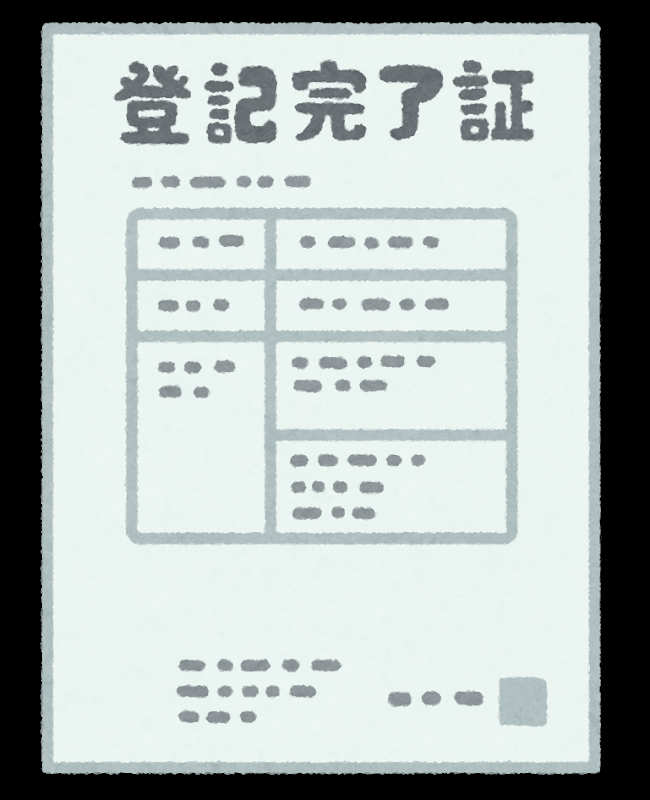使用貸借契約について
2021年もあと半月。2021年は東京オリンピックが開催され、日本中に活気を与えました。
一方、新型コロナウィルス感染症への懸念は収まることなく、まだまだ皆さまの行動に影響を与えることでしょう。
話は変わりますが、今回は使用貸借契約について述べていきます。
皆さまが現在住まれているご自宅が賃貸あるいは身内の方が所有している物件である場合、賃料は発生していますか。発生している場合、居住者が賃料を払われていますか。もし、居住者が賃料を支払っていない場合、税金がかかる可能性があります。
例えば親子間において、親が子の住む物件の賃料を払っている、親が所有する物件に子を無償で住まわせるケースは少なくありません。このように、貸主が借主に対して目的物を無償で使用収益させ、借主は契約終了時に目的物を返還する合意を使用貸借契約(民法593条)といいます。これに対し、借主が貸主に使用収益の対価を支払うことを賃貸借契約といいます。
使用貸借契約は上述したように、親族間では民法上扶養義務が生じているため無償で貸し付けた場合でも、経済的利益が少額であり、課税上弊害がないと認められる場合は、贈与税を課さないこととされています(相続税法基本通達9-10)。ただし、その扶養義務の履行範囲を明確に示した条文はないため、事実認定が必要となります。例えば、賃料の金額が相場として適正なのか、受け取る子の年齢や支払能力など、客観的事実に対して適正な説明を要するケースがあります。
もし、賃料が適正でないとして、賃料全額が使用貸借契約に基づくものではないと判断された場合は、子に対して贈与税が課される可能性もあります。
したがって、親子間の賃料のやりとりには、充分な事実認定を検討する必要があります。
また、使用貸借契約書についても当事者間で内容をしっかり認識しておく必要があります。認識がなかったとしても、契約書への署名・押印に至る経緯、取引実態等で契約が成立していたと判断されることもあります。今年土地の使用貸借契約の有効性について争われた裁判事例も起きています(大阪地判令和3年4月22日裁判所HP参照、平成31年(行ウ)51号)。
使用貸借契約は、親子間の賃料のみを考えると無償になるメリットがあるかもしれません。しかし、借主がそのまま転売したり、賃貸したりするとなると、貸主や借主に返還義務があるのか、貸主や借主が死亡した場合使用貸借契約は継続するのかなど様々な問題が起こるケースがあります。
川庄公認会計士事務所
嶋村
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。 ...
相続・事業承継コラム 2024-03-22
4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...