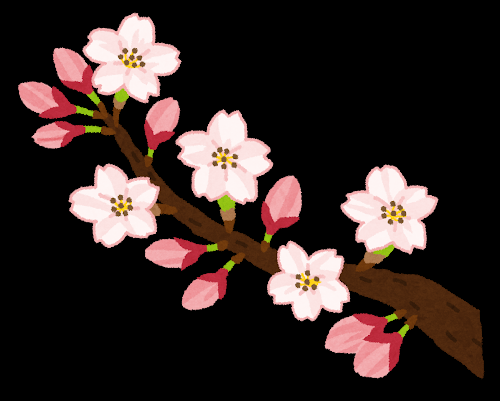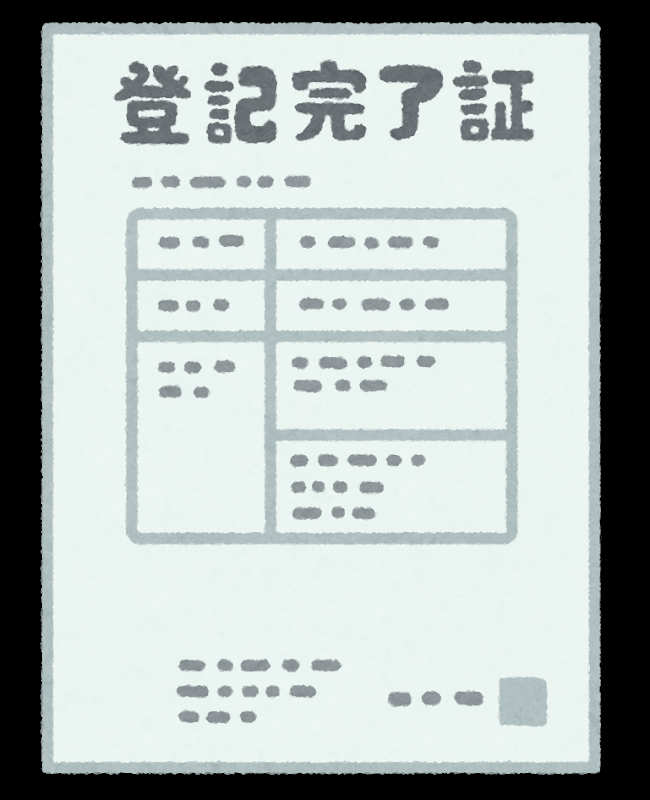住宅取得等資金を贈与された場合の贈与税について
住宅を購入するための資金を親御さんから頂くことがあると思います。そのようなお金をもらった場合は、通常贈与税が課税されることとなります。
しかし、一定の要件を満たし手続きをした場合には、この贈与税が掛からないことがあります。それが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」と「住宅取得等資金を取得した場合の相続時精算課税の特例」というものです。これらの制度は平成21年に租税特別措置法にて創設され、平成27年度税制改正にて延長される事になりました。今回が2回目の延長となります。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は、贈与税を一定額まで非課税にするというものです。この制度の適用を受ける為には一定の要件がありまして、その要件とは以下の通りです。
1 受贈者(もらう人)の要件
(1) 日本国内に住所がある人又は日本国内に住所はないが日本国籍のある一定の人
(2) その年の1月1日において20歳以上の方
(3) その年の合計所得金額が2,000万円以下
2 贈与者(あげる人)の要件
受贈者の直系尊属(もらう人の両親・祖父母等)
3 購入・新築等する住宅等の要件
(1) 住居用の家屋又はその土地等
(2) 住居用の家屋に贈与された年の翌年3月15日までに住む事又は住む事が確実であると見込まれること
(3) 住宅を購入・新築等する業者が受贈者と特別の関係のある者でないこと
以上の要件を満たすと一定の金額まで贈与税が非課税となります。その一定の金額は以下の通りです。
4 非課税限度額

(注1)非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
(注2)住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記2の表には該当しません。
(注3)住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日
新非課税制度の適用を受けるためには、平成 31 年6月 30 日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
(注4)省エネ等住宅〔平成 24 年3月 31 日 国土交通省告示 389 号・390 号〕
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
一方、「住宅取得等資金を取得した場合の相続時精算課税の特例」は、2,500万円まで贈与税が掛からない代わりに、その贈与者が亡くなった際、その贈与により取得した住宅取得等資金を相続財産に入れて相続税の計算を行う制度です。この制度の適用を受ける為にも一定の要件がありまして、その要件とは以下の通りです。
1 受贈者(もらう人)の要件
(1) 日本国内に住所がある人又は日本国内に住所はないが日本国籍のある一定の人
(2) その年の1月1日において20歳以上の方
(3) 贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含みます。)
2 贈与者(あげる人)の要件
3 購入・新築等する住宅等の要件
共に上記非課税制度と同じです。
これらの制度は上記以外の細かい要件がありますが、相続対策として有効なものとなりますので、適用される際には川庄事務所までご相談下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田口 由多加
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。 ...
相続・事業承継コラム 2024-03-22
4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...